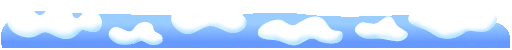
トップ>物語>
トゥーラ年代記
■残日の光
作者:おとわ様
淡い木漏れ日のように微かな夕暮れの日差しが射し込み、彼の視線
の先にあるものを照らし出していた。
降りかかる光と同じく淡い色彩が放つ優しさは見る者の心を一瞬解き
放つように穏やかに見える。
幸福そうな顔をして丸まった猫と眠たげに寄りかかる鼠。本来は仇敵
であるはずの彼らはそこでは無類の友であるかのように自然に寄り添
っていた。
よくよく見れば、その小動物たちは本来の姿とは少々違っている。柔
らかな体からは想像しずらい力強さを持つ翼がその背にはあるではな
いか。
見慣れないその生物たちはこの大陸には生息しない者たち。幻の獣
たちだ。その翼は不老不死の霊薬の材料になると言われている。しか
し安穏とした彼らの姿から、その効能を謳われる薬を連想するのは難し
かった。
じっとそれをじっと見つめていた彼の瞳がふと伏せられる。何かを想
い出すように長い睫毛が震えた。
「あの二人は元気でいるのだろうか?」
再び顔をあげると、目の前に掲げられた絵画……幻獣画をまじまじと
見つめる。そしてあるかなきかの小さな吐息を吐いた。
背後の足音にふと我に返り、彼は振り返る。その足音から近づいてく
る者の正体はすぐに知れていた。
ずらりと並んだ書棚の間を縫って一人の男が近づいてきている。大理
石の床にその足音だけが高くこだましていた。
「兄上。よくここがお判りで……」
「お前が一人で考え事をするときはここにいると教えてもらったんだ、我
が外務卿閣下」
明るい茶色の髪を短く刈り込んだ精悍な顔立ちの男が自分を見下ろ
している。ずいぶんと背の高い男である。平均的な身長よりは頭一つ
半分は高いだろう。
一瞬だけ男の視線が絵画へと向けられたが、別段感銘を受けた様子
も見えない。
「騎士団領の連中がまたぞろ動き出している。外務省の奴らはお前の
頭に頼り切りか? こんなところへ入り浸るほど頭を悩ませているとは」
「無能揃いのように言わないでください。私はここに息抜きにきているだ
けです」
再び絵画へと視線を向けると彼は小さなため息をついた。茫洋とした
色を広げる絵画は彼の吐息にも沈黙したまま、壁の片隅に鎮座してい
る。
「また疲れた顔をして。諦め悪くウジウジするくらいなら、さらってくれば
良かったじゃないか。お前は時々間抜けなくらいに禁欲的なことをする
な、ミレル」
ぶっきらぼうな兄の声にギョッとして彼、ミレルは背の高い兄を振り返
った。くしゃくしゃと前髪を掻き、口を尖らせる様は自分よりも年下ように
も見えるから不思議だ。
太い眉の下で悪戯っぽく兄の瞳が光るのをミレルは見逃さなかった。
思わず次の言葉に身構える。
「今からでも遅くないぞ。さっさと嫁さん連れてきて俺に紹介しろ。つい
でに俺の代わりに跡継ぎを作っておいてくれたら言うことなしだ」
にやりと口元に浮かんだ笑みがまるで悪戯を仕掛ける子供のような
表情を兄に与えていた。
ミレルは思わずギロリと兄を睨む。またいつものようにからかっているのだ。
「跡継ぎを作る仕事は兄上の役目です。私に押しつけないでください。
だいたい、側近の目を盗んで城下へ忍んでいくのに、どうして浮いた話
の一つも聞こえてこないんですか!」
大袈裟に首をすくめて見せた兄が苦笑いを浮かべている。天窓から
漏れる残日の輝きに縁取られて、日焼けした顔が常よりも若く見えた。
「しまった。やぶ蛇だったか」
小さく舌を出した兄の態度にミレルは怒りを収める。忙しく政務をこな
す兄に、浮いた話一つ出ないほどの重圧をかけているのは、他でもな
いこのトゥーラという国そのものだ。
いや、かつて兄の浮き名が聞こえてきたことがあった。しかしその相
手の娘は無惨な殺され方をしたと聞く。反王派の者の仕業だとも、敵国
の仕業だとも噂されたが、真偽は未だに闇のなかにある。
王位を継いだときの混乱から脱却したとはいえ、兄の周りには常に暗
殺の魔手が迫り、血の匂いが絶えない。おちおちと縁談の話などでき
たものではない。
「まぁ、お前は王様じゃないからな。……好きにやれよ」
自分に都合の悪い話を振られそうになり、慌てて背を向けて退散して
いく兄の背には王のマントが重たげにかかっていた。まるでそれ自体
が兄に重圧をかけているような錯覚に、ミレルはふと目眩を感じる。
あれは父が羽織っていたものと同じ意匠のものだ。歴代の王が、その
背格好に合わせて作り替えてはいるものの、王家の紋章を象った意匠
を縫いつけたマントは王たちをその責務に縛りつけるように常にその背
にあった。
「……兄上」
自分の小さな呼び声にふと兄の足が止まった。
「おっと、忘れるところだった。もうすぐ各国の大使とその夫人方を招い
ての晩餐会があるからな。お前、女たちを足止めしておけよ。俺は脂粉
まみれになるのは御免だ」
変わらず悪戯っぽい口調のまま兄が振り返り、意味ありげに口元を
歪める。おおかた、大使夫人とご令嬢たちを自分に押しつけて、自分だ
け行方をくらまそうとでも考えているの違いない。
「じゃ、爺さんたちの相手は兄上がしてくださるんですね。あぁ、良かっ
た。ヒヒ爺たちになで回されるなんて気色悪いですからね」
芝居がかった仕草で肩をすくめてみせ、ミレルは剣呑な視線を兄に向
けたあと、嫌みっぽくそっぽをむいた。
「おいおい……。勘弁してくれよ」
さも厭そうに顔を歪める兄の様子にミレルは、してやったりと笑みを漏
らす。ほとんどの相手を口先だけで丸め込んでしまう兄が、なぜか自分
にだけは弱いことをミレルはよく知っていた。
いや……計算ずくで行動する兄が唯一その策謀を度外視して接する
者は自分だけだと自惚れているだけかもしれないが。
「たまには逃げ出さずに最後までつき合ってくださいよね。……ところ
で、本当はなんの用だったんですか?」
「いやなに……弟が惚れた女の描いたという絵を拝見しにきただけだ」
しれっと答えを返してくる兄に再び剣呑な視線を向けると、ミレルは表
情を殺した。
「誰です? そんな不埒な噂を流したのは?」
宮廷に仕える役人たちならミレルのこの顔を見ただけでとんでもない
ことを口にしてしまったのだと気づいただろう。
女性的な外見に似合わぬ剛腕を奮う外務卿として国内外に知られる
ミレルは、自分の欠点であるその外見すらいつも利用していた。この優
しげな顔で相手に対するとき、初対面の者はほとんどその外見に騙さ
れて油断する。彼が油断ならない性格の持ち主だと気づく頃には、ミレ
ルは相手の分析を終えてしまっているの常だ。
その彼が相手を睨むなどということは、それはよほどの失態を犯した
か、あるいは逆鱗に触れるようなことを口走った者に対してだけだ。
「おっかない顔をするなよ。休暇から帰ってきた外務卿が、寄贈した絵
画を眺めに日がな一日この王立図書館に入り浸っていたんじゃ噂も立
つさ」
「私は気分転換にきているだけです。不愉快な!」
珍しく語気を荒げるミレルに兄王が苦笑し、再びチラリと幻獣画へ視
線を向けた。
「猫のように気まぐれな女なのか、鼠のように賢しい女なのかは知らん
が……掴まえておかんと、女は待っててくれないぞ」
「だから! どうしてそういう話になるんですか!」
顔を上気させて唸り声をあげるミレルが面白いのか、兄王はクツクツ
と喉の奥で笑い声をあげている。三十になり、そろそろ落ち着いてもい
い頃なのだが、この兄は子供っぽい悪戯を止めようとはしない。
「私をからかってそんなに面白いんですか!?」
茹でタコのように顔を赤らめているミレルに国王はノシノシと近づいて
くると、その頭に厳つい掌を乗せた。
「まぁまぁ、そう興奮せんと。少し落ち着け。他の者に迷惑だ」
弟の自分よりも薄い色をした髪をくしゃくしゃと掻き回して、王は
三度(みたび)、目の前の幻獣画へと視線を向ける。どこか遠くを見るよ
うなその瞳の先に絵は静かに掲げられていた。
木漏れ日のような陽光のなかに異形の獣たちはまどろんでいる。静
謐だが陽気で温かい光が彼らを包み、それはひどく幸福そうな姿に映
った。辺りは日暮れで薄暗いほどなのに、この絵のまわりだけは小春
日和の穏やかな輝きが満ちあふれているようだ。
「……いい、絵だな」
兄の視線を追ってミレルもじっとその絵を見つめた。
「当代きっての絵師の筆によるものですからね」
まるで自分が褒められたようにミレルは胸を張る。その誇らしげな弟
の横顔を盗み見た兄王の口元に自嘲が浮かんだ。
「ミレル……俺に遠慮なんかするなよ?」
驚いて振り返ったミレルの視線の先には、マントをひるがえして歩み
去ろうとしている兄の背中が見えた。
「兄上……!」
再度の呼びかけに、先ほどと同じように兄王の足が止まる。しかし今
度はチラリと肩越しに視線を返しただけで向き直ろうとはしない。
「惚れた女と一緒になるのに、早いも遅いもない。俺の結婚なんぞ待っ
ていたら、お前、すぐに爺さんだぞ」
早口にまくしたてる兄の肩が常よりも強ばって見えた。自分よりも頭
一つ分は背が高いはずの兄を、このときばかりは年端のいかない少年
のように感じてミレルは口ごもる。
返すべき答えは身の内のどこを探しても見つからない。いや……見
つけた答えを返そうものなら、きっと兄は余計に傷ついた顔をするだろ
う。
押し黙ったミレルを残して王は歩き始めた。もう振り返ろうとはしない。
それを立ち尽くしたまま見送るミレルの脳裏に、可愛がっていた動物の
骸を前に吼える兄の声が蘇ってきた。
『この獣を見よ! ミレル! これは、弱いから殺されるのだ! 爪も牙
も持たず、柔らかな肌をしているから殺されるのだ! 己が庇護されて
ると、思っているから……思っているから殺されるのだ!!』
あの動物にもこの絵のように翼があった。のんびりとした外見は河馬
に似て、おっとりとした気質は誰にでも愛される可愛らしい動物だった。
あの日、物言わぬ骸の前で牙を得ることを誓った兄に、自分も誓って
いる。
「後悔などしておりません、陛下」
疲れを感じてミレルは肩を落とした。そしてもはや何度目か判らない
吐息とともに壁の幻画に見入る。
この絵を手渡した細い腕を想い出す。
『父の最後の作品よ。あなた持っておいでなさいな。……もうあの指で
は筆を握れないからね』
つんと顎をあげ、誇り高い横顔をした娘が押しつけるようにしてこれを
手渡してきたのだ。夕暮れに紅く染まった瀟洒な南方風の建物の一角
で、彼女は今も父親とともに遙かな海を見つめているのだろうか?
病床に伏した父親を守る娘の横顔はひどく兄に似ているような気がし
た。陽気な外見とは反対に、張りつめた糸のような緊張を身の内に抱
えて……。
『もうわたししか守る者がいないでしょう?』
淡々とした口調でこれからの生活を語る女の声と、兄のなかにある慟
哭がミレルの脳裏を去来し、重なり合った。
「後悔などしていません。兄上を助けるのだと誓ったのは私自身です。
そのために払う犠牲など……」
かすれた囁き声を聞く者はない。ただ目の前の絵画だけが彼の声音
に耳を傾けるのみ。
じっと物言わぬ絵に視線を向けていたミレルがゆっくりと胸を張った。
女性的で優しげな顔立ちに気怠い表情を浮かべたまま、彼は静かに
絵と向き合っている。直立不動の姿勢で幻獣画と対峙する彼は、まる
で彫像のようだった。
どれほどの時間そうしていただろう。夕日はついに没し、あとは最後
の残光だけが天窓から弱々しい光を落としている。
突然、ミレルはきびすを返して歩き始めた。一度も背後を振り返りはし
ない。仮面のように殺した表情には気怠さは消えている。
見上げるほど高い書棚が暗闇にのっそりと立ち上がり、彼が通り過ぎ
る様を伺っているようだった。そして消え残っている暮色に照らされた絵
と共に彼の背を見送る。
それを感じ取っているのか、ミレルは振り切るように大理石の床を鳴
らして歩き続けた。足早に歩く彼を追ってくる者は誰もいないというの
に、彼は何かに追われるようにして暗い廊下を歩く。
『力が欲しい。この身に爪と牙があれば、国にあだなす魔物どもを、城
から永久に消し去るものを』
そう願って手に入れた力であるはずだ。それを後悔してなどいない。
その願いのために支払う代価がどんなものであれ、後悔するなど傲慢
ではないか。
残日の光を宿した鈍い空が廊下の窓から見える。その空はまるで先
ほどまでのミレルの表情を写し取ったかのように気怠げな色をしてい
た。
きららかな陽光は去り、夜の帳(とばり)がすぐそこまでやってきている。
その最後のか弱い光のなかをトゥーラ王国の外務卿は胸をそびやか
し、傲然と歩き続けた。
終

本編へ
プラモ&パズル まじっく トップへ